家の中での親の悩みの1つに『子供が片付けをしない』ことがあります。
何度言ってもなかなか直らず、途方に暮れている方もおられるでしょう。
ちょうど同じ頃、子供はこんなことを考えているのかもしれませんよ。

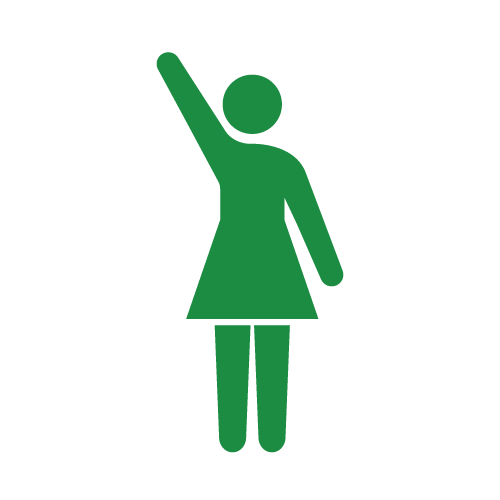
ここでは、そんな子供たちと、格闘し疲れたお母さん方のために『片付けせずにはいられない!?親子での上手な片づけ方』を一緒に考えていけたらと思います!
1.子供が片付けられない原因は親にないか?
子供が片付けられないことを、子供の責任にしてしまう大人(親)は多いと思います。
それは、
・大人は、使ったものは使った場所に戻すから
自分が「本当にいつも」できているかはさておき
・大人は、散らかさないから
長い人生で、片付けの方法を習得してきたから。
子供よりも、試行錯誤して新しいことを学ぶ機会が減っているとも言えるが
・大人は、…
お分かりの通り、全て『大人の世界』が基準になっています。
しかし、その一方で子供たちは、こんなことを考えているかもしれません。
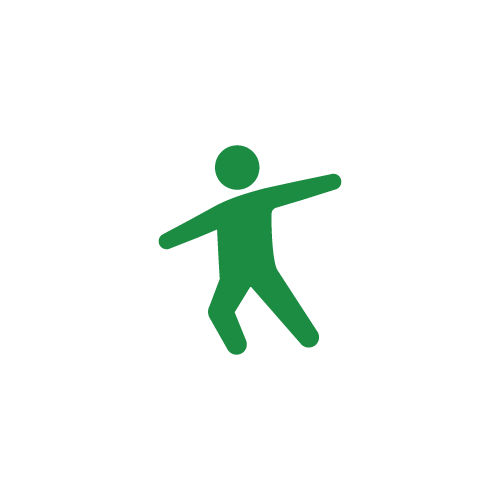
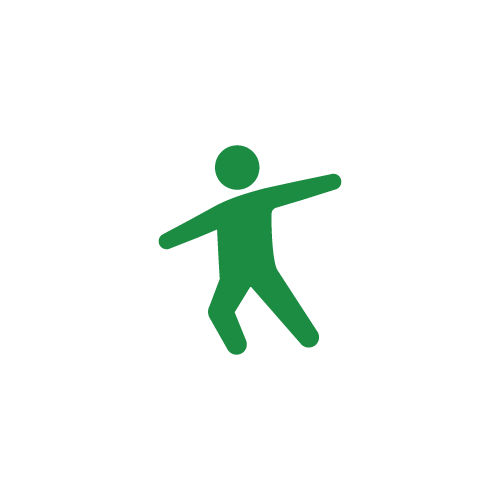

普段は大人の怒りで見えない子供たちの『本音』の中に、片付けが上手にできるようになるヒントが隠れている気がしませんか?
②片付ける環境がムダに複雑ではないか?
③子供とルールをしっかり決めているか?
2.片付けの意味と基本を大人も確認しよう!
子供の片付けで悩む親御さんの中には『実は自分も片付けできないんです!』
そんな大人も少なからずいるかもしれません。(私もです)
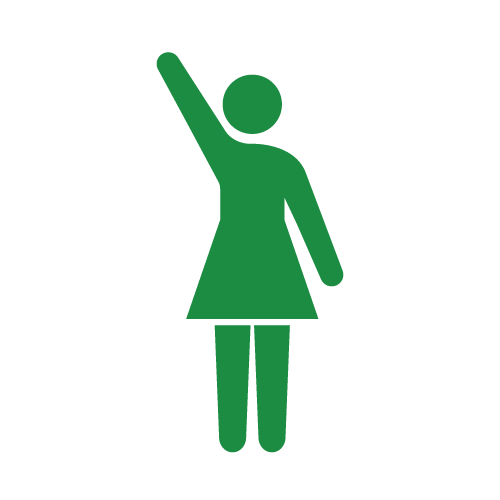
ここでは、そんな大人の方と一緒に『片付けする意味(メリット)』と『片付けの基本』について大まかなに考えてみます。
大人はバッチリ!という方は、さらっと『子供が自然と片付ける方法』まで読み進めてください!
⇒散らかった光景を見るだけで『集中力』は下がります。
②必要な物がすぐ手に入って、時間(探す)・お金(二度買い)をムダにしない!
③自分が本当に必要なものが見えて、ムダにものを持たなくなる!
これだけでも、部屋がスッキリする以上の大きな効果があると思いませんか?
片付けの基本とコツをおさらい!
片付けの基本は、
⓪物をへらす
⇒散らかりやすいものは『いらないもの・保留できるもの』ではありませんか?
①物の場所を決める
⇒使う場所と収納場所を限りなく近づけることで、『使いやすく、しまいやすい環境』を目指す!
②物の所有者・管理者を決める
⇒共有(管理者不明)のものは散らかりやすい。
③物を使うルールを決める
⇒意外と軽視されがちな『使う時間』ルール
3.子供が自然と片付ける方法①環境づくり
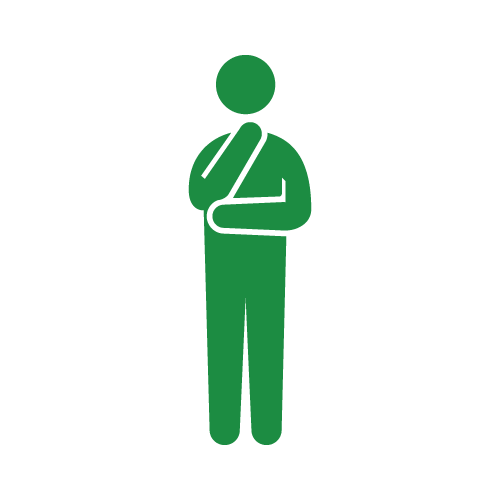
ここでは、そんな『子供が自然と片付けたくなる!理想の環境づくり』について、考えていこうと思います。
①片付けしたくなるような大切なものだけある
②片付けないとまわらない数しかない
◎使いやすく、しまいやすい!
①「しまう場所」が分かりやすい!
②「使う場所」と「しまう場所」を近づける!
③「使うまで・しまうまで」の手順を少なくする!
※逆手にとって、子供に使ってほしくないものは「使いにくい」ようにする方法も!
必要なものが必要なだけある!
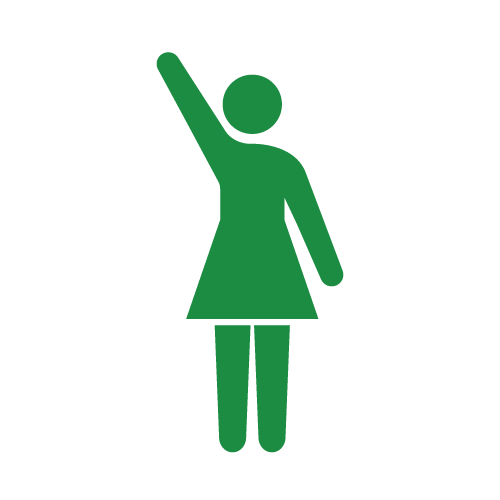
片付けしたくなるような大切なものだけある
まず、自分の宝物を思い浮かべてみてください。
その辺にほったらかされているのを見つけたら、(そもそもほったらかさないと思いますが)、すぐに大切に保管しますよね。
子供にとっても同じです。
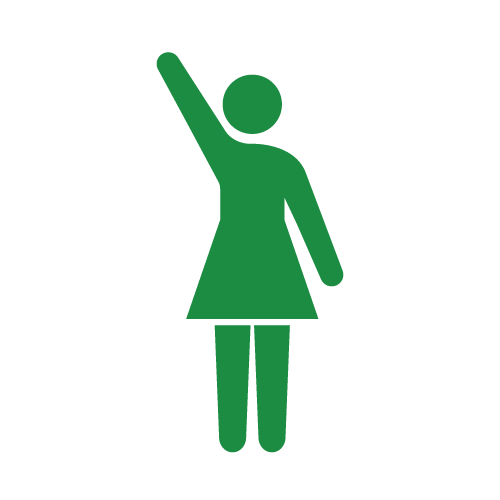
・大人が気に入っているだけではありませんか?
⇒子供が気に入っていなければ、思い切って廃棄。
どうしても子供に遊んでもらいたいなら、管理者を大人に変更しましょう。
・せっかく買ったからと未練があるだけではありませんか?
⇒それは子供が気に入らないものを教えてくれました。
役割を終えたので、気持ちよく廃棄しましょう。
すぐ手放せば中古品でも高額で次の買い手が見つかるかもしれません。
物の気持ちを代弁する
物を大切にすることにつながりますが、散らかったままの物の気持ちを代弁するのも良いでしょう。
転がった鉛筆「おうちに帰りたいわ~」
脱ぎ捨てられた服「みんなのところに戻りたい…」
棚に押し込まれたプリント「押しつぶされてイタイ!」
物を人にたとえることによって、子供が物の状態を共感として理解しやすくなるのではないでしょうか?
片付けないとまわらない数しかない
『使いやすく、しまいやすい』保管場所とは?
物を充分に厳選できたら、あとは上手に管理していきましょう!
最初に「しまう(保管)場所」をしっかり決めることが大切ですね。
この、しまう場所を決める時にも、コツがあります。
『しまう場所』が分かりやすい!
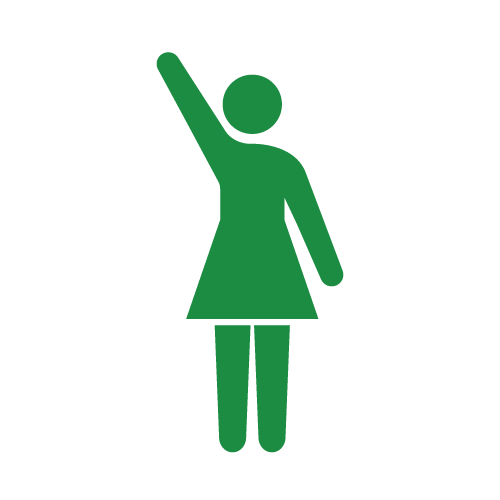
カテゴリ別にBOXがあるのはよくあると思うのですが、私が一番衝撃を受けたのは、
『BOX前面に保管された状態の写真をはる!』
これは最強です!
保育園児でも片付けできる方法ですね。
準備はやや面倒ですが、今やスマホの写真をコンビニでコピー感覚でプリントアウトできる時代ですから、荒れやすいところから少しずつやるのも良いかもしれません。
写真が大変なら、
・しまう場所が同じものに同じシールをはる
・見出しに絵をつけてあげる
・テプラでアイコンつき見出しを活用する
などの工夫も参考にできるのではないでしょうか。
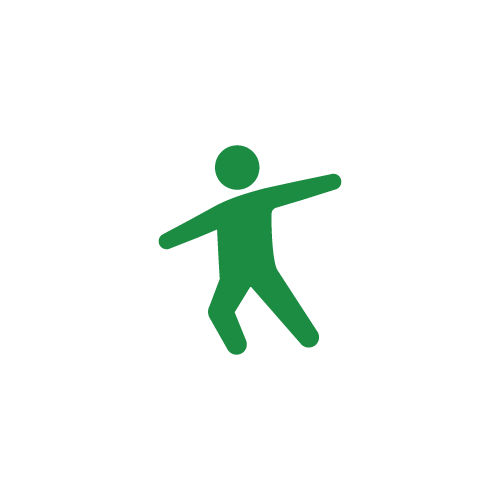
こんな子供の本音が聞こえてきませんか?
使う場所としまう場所を近づける
収納場所の制限の問題もありますが、実は生活の中には、ナゾの常識にとらわれて、使う場所としまう場所が離れているものが、結構あります。
子供バージョンで言いますと、
・おもちゃ箱は2階子供部屋、遊ぶのは1階リビング
・ランドセル置きは2階子供部屋、家では宿題くらいしかしない。
・クローゼットは2階子供部屋、風呂は1階
1階で遊ぶおもちゃは、1階で管理すればよいし、
重たいランドセルも玄関においておけばよいはずです。
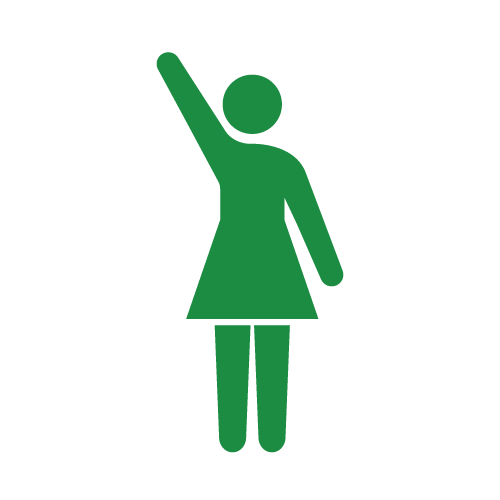
これまでの常識にとらわれず、散らかりやすいものは、まず「使う場所としまう場所の距離が遠くなっていないか?」確認するところから始めてみましょう!
部屋・場所でコンセプトをはっきり!
しまう場所を考える上で、一番てっとり早いのは、『部屋・スペースでコンセプト(用途)をはっきり区分けする』ことです。
キッチンや風呂などは、目的がはっきりしているのに、散らかりやすいリビングとか多目的室?は、
『何でもできて、ゆっくりできる場所』
のように目的がぼんやりしていませんか?
このぼんやりスペースの中を、しっかり区分けしてしまいましょう。
●用途別
・勉強⇒宿題(書く)、読書(読む)、習い事など
・遊び⇒お絵かき・工作(材料)、同形バラバラ系(ブロック・レールなどパーツ)、室内運動、メディア(TV・ゲーム)
●家族(兄弟)別
・子供部屋の確保
・共有スペースの割り振り
(リビング、ダイニング机など)
実際に、マットを敷いたり、線引きしたりするのもアリですね!
そして、もちろん使う物はこのエリア内(もしくはごく近く)にしまうようにします。
場所を用途でしっかり分けることで、物が別のエリアに無限にひろがって行きにくい!というメリットがあります。
「使うまで・しまうまで」の手順を限りなく少なくする!
片付けの手順が多ければ多いほど、子供の片付け意欲がどんどん下がってきます。
どんな小さな手間も減らしてあげられるように努めましょう!
◎かける!ふたなし!で片付け手間半減!
BOXを持ってきて、ふたをあけて…
子供にとっては(無意識ではきっと大人も)、そんなことも『手間』と感じてしまうようです。
手間は、できる限りはぶいてあげましょう!
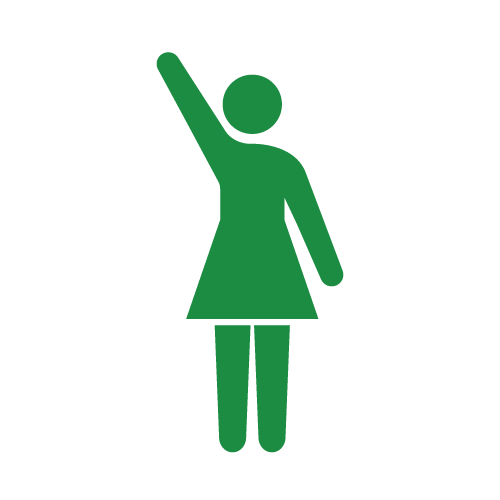
◎一緒に使うものはセットで保管
一緒に使う物は、1度に全部使えるように保管するとラクです!
・いつものセット(登校セット・旅行セット)
・ながらセット(ドライヤーと書籍、学校カバンと紙ごみ箱)
・イベントセット(お菓子づくり用具・ラッピング・パーティーグッズ)
◎カテゴリーを細分しすぎない!
使いやすく・しまいやすく、するのに『分類』は必要不可欠ですが、分類するのに頭を使いすぎては、片付けしてるのか、新たな別の作業をしているのか、分からなくなってきます。
分類は必要最低限で、さくっと片づけられることを最優先にしましょう。
凝り過ぎにもご注意ください。
子供お気に入りBOXを作る!
子供の遊び方をじっと見ていると分かるのですが、大人には思いつかない、すごい組み合わせのものを使って、何らかの世界を想像・創造しています。
なので、片付けの段階で大人ルールのカテゴリーに分けられると、それはそれでストレスかもしれません。
大人にはよく分からないその組み合わせを壊さないよう、子供が好きに詰め込める『お気に入りBOX』を子供ごとに持たせてあげたら、それだけで子供も喜んで片付けに参加してくれるかもしれません。
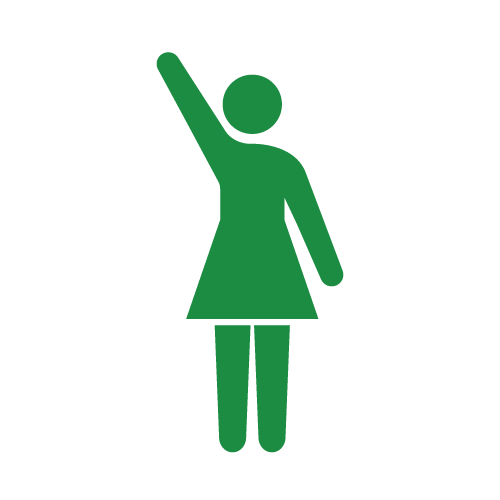
・清浄綿数枚
・サイコロいくつか
・小さな電卓
・みかん数個
が出てきて「これから遠足に行く」と言い出しました。
前半はみなお金のつもりらしいですが…遠足にそんなにお金いる?(笑)
4.子供が自然と片付ける方法②ルール
環境が整ったら、あとは大人とのルール作りです!
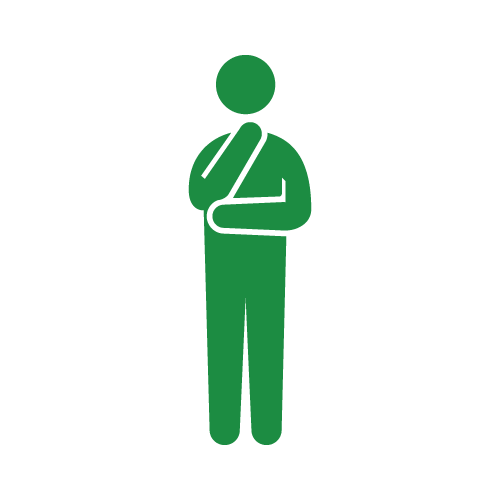
そう思っているなら、子供を怒るのはやめた方が良いかもしれません。
ここでは、子供が片付けられない!に隠された、ルールの落とし穴について考えていこうと思います。
片付けで忘れがちなルール①『時間』
子供の散らかしと大人のイライラの間に、大事なルール決めが1つ抜けていませんか?
それは『時間(期限)』のルールです。
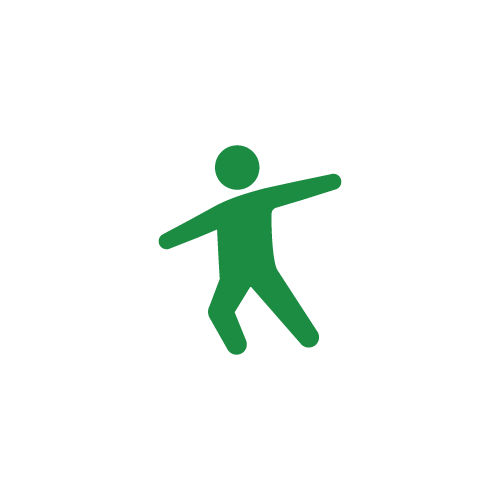
「もうすぐご飯だから、そろそろ片付けようか…」
ができるのは、大人の常識なのです!
なので、まずは子供と『時間(期限)のルール』を決めるところから始めませんか?
時間(期限)のルールの決め方
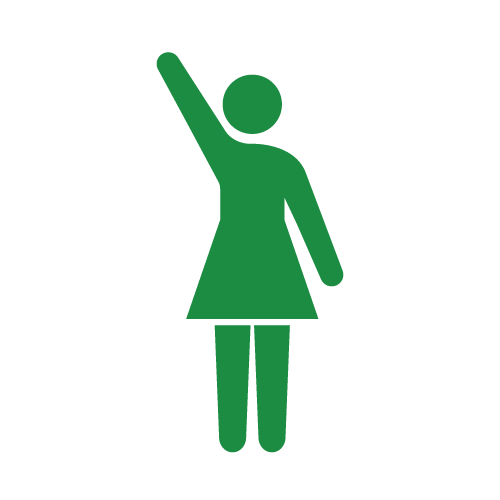
これでは、子供も『(きょとん)?』です。
まずは、大人が『散らかし』を黙認する時間を、しっかり親子で最初に決めておくことです。
これなら、子供たちも片付けする心の準備が整うかもしれません。
子供も、自分がした約束とあれば、しっかり守る努力はしてくれますよ♪
できれば、毎日同じ時間にすると、習慣になって、より良いです!
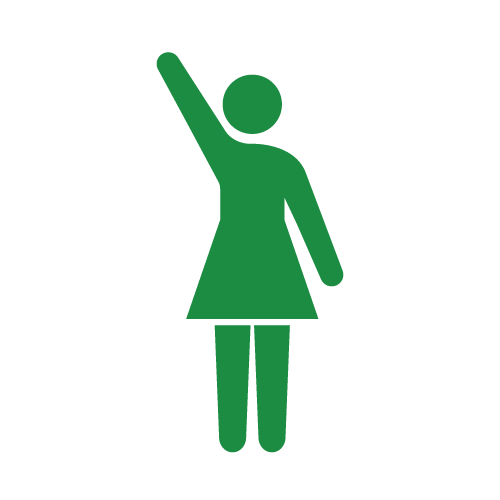
片付けタイムを作る
もう1つは、幼稚園などでおなじみの『お片付けタイム』です。
これ、おうちでもしっかり作ってあげられてるでしょうか。
片付けタイムの使い方は、以下の2パターンが考えられるでしょうか。
●片付け方法を教える!
⇒『親子で一緒にお片付け(前向きな声かけ)』
●片付けをできるだけ短く効率よく!
⇒『お片付けタイムトライアル(見守るだけ)』
2つ目を子供だけでやってもらう場合は、最初にしっかり片付け方法を教えて(決めて)おかないと、子供が戸惑ってしまいますので注意!
大事なことは『親子で納得できる片付け』を見つけることです。
片付けタイムが子供にとってイヤなものにならないよう、親もイライラ指示ばかりしないように注意!
そして、きれいになったら大げさに喜ぶ!
(ほめるより効果アリ♪)
片付け中は温かくサポートor完全に任せる、のいずれかにしておきましょう。
音楽をかけるのも良いでしょう♪
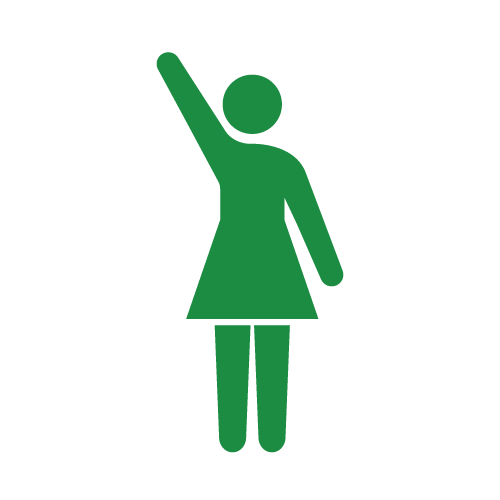
片付けで忘れがちなルール②『管理者』

子供の片付け逃れの言い訳に、こんなフレーズがありますね。
確かに、自分が出してもいないものを片付けさせられるのは、不満に思うかもしれません。
こんなことにならないよう、あらかじめ、物(収納場所)ごとに『管理者』を設定しておきます。
②共有物(共有スペース)でも管理者を決める
(よく使う人など)
このようにすれば、『誰が片付けるのか?』を決めるムダな時間も削ることができます。
片付けで忘れがちなルール③応急措置
ある程度ルールを決めていても、
・遊びに夢中になってつい時間を過ぎてしまった!
・制作が途中!片付けたくない!
いろいろな理由で、約束通りに片付けにとりかかれない場合もあります。
こんな時はどうしたら良いでしょう?
こんな場合も、頭ごなしに怒るのではなく、大人が先回りして考えておいてあげることも大切です。
とりあえずBOXは有効か?
片づけ中に『これってどこに片付けたらいいんだろ?』というものが出てきたり、他の用事とのかね合いで、しっかり片付けられなかったりする時がありますね。
そんな時の救世主!『とりあえずBOX』
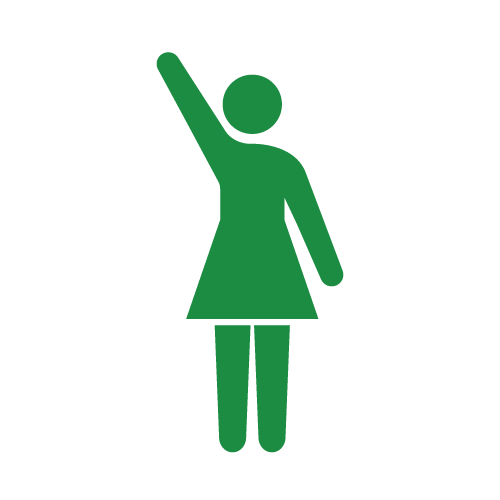
目の前の散らかりが素早くきれいになるだけで、大人のイライラもすっと収まるからです。
ただし、これはあくまで応急措置です。
本来は、持っているものとの付き合いがしっかりしているおうちでは不要なはずです。
・とりあえずBOXばかり、いつもいっぱいになる
・いつも同じものが入って来る
こんな場合は、『管理方法は適切か?』『そもそもそれって本当に必要?』
もう一度、持ち物を見直しをした方が良いかもしれませんね。
作品は壊さないで飾る!
ブロックなどでせっかく途中まで作り上げた『傑作』を、箱に戻すためにバラバラにされるのは、辛いものです。
こんな時は思い切って『飾って保管』しましょう!
子供も大満足で、片付けに参加してくれます♪
ただし、何でも飾るとかさばるので、飾る分をあらかじめ決めておきます。
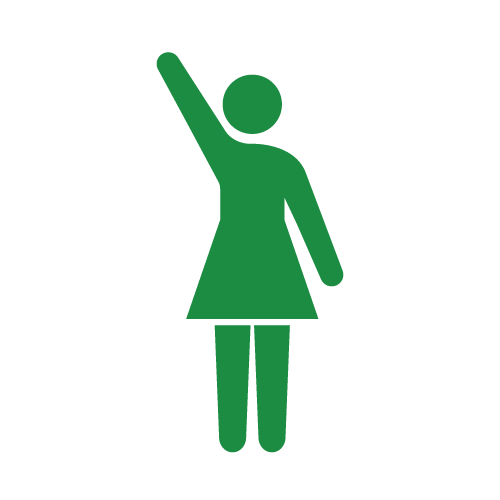
5.【まとめ】子供が片付けられるように環境・ルールを整えよう!
子供が片付けられるようになるためには、大人たちの意識をかえて環境やルールを見直すことから始めることが必要だと分かりましたね!
子供との「片付け」を通じて、自分にとって本当に大切な物の見きわめ、物を大切にすることをお互いに学ぶことができたらうれしいですね。
・自分(大人)は片付けができているか?
・片付ける方法がムダに複雑ではないか?
・子供とのルールをしっかり決めているか?
2.片付けの意味と基本を大人も確認しよう!
・片付けをすると、ムダがなく人生がとても充実する!
・片付けの基本は、『場所・管理者・ルール』をしっかり決めること!
3.子供も自然と片付けする!環境づくりは?
・必要なものが必要なだけあれば、散らかりにくい!
・『使いやすく、しまいやすい』と片づけやすい!
・『使う』と『しまう』の距離・手順を少なくする!
4.子供も自然と片付けする!ルールづくりは?
・時間(期限)を決めて、片付けの心の準備を。
・管理者を決めて、片づけをスムーズにする。
・『とりあえずBOX』も時にはOK!
・子供の『傑作』は、飾って片付け!
